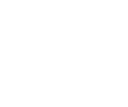分げつのころ。つばめもカエルもゲンゴロウも。

約10年の年月をかけて生まれた、兵庫県オリジナルの新しいお米「コ・ノ・ホ・シ」。
いよいよ2025年秋、私たちの食卓に並びます。
田植えから出荷までのコ・ノ・ホ・シの様子を連載でお届け。
第1回は「分げつ(ぶんげつ)」です。
3〜4本の苗が、
なんと20本以上に増える!?
7月初旬、5月に田植えしたコ・ノ・ホ・シを見に行くと、すでに膝くらいの高さまで成長していました。田植えに使うのは12センチほどに成長した苗。人工芝のようにシート状にまとまって育成されている苗を3〜4本ずつに分けながら水を張った田んぼに植え付けていきますが、実はこの稲、3〜4本のまま成長していくわけではないんです。
苗が根を張りぐんぐん伸び始めると、なんと茎の根元から新しい茎が出てきます。これを「分げつ」と呼び、3〜4本の苗は20本前後になります。コ・ノ・ホ・シはこの「分げつ」の力がとても強く、7月初旬には30本前後に増えていました。ただ、分げつが多ければ多いほど良いというわけではなく、あまり増えすぎてしまうとその先につく穂に栄養が行き渡らなくなるため、20〜30本ほどが“ちょうどいい”状態なのだそう。

田植え直後の稲(写真左)と、さらにそこから1ヶ月経った状態の稲。株元からぐんぐん茎が出て分げつが進み、力強く育っているのがわかります。
とはいえ、「もう分げつしなくていいよ〜」と言っても稲には伝わらないので、分げつ具合をコントロールするのも米農家さんの腕の見せ所。“水の量”がポイントになります。田植え後に田んぼの水を少なめに保つと根に酸素が行き渡りやすくなるため茎数が増え、逆に多めにすると茎数は増えにくくなるのだそう。分げつがちょうど良い頃合いで田んぼの水を抜いて地面を乾かす「中干し(なかぼし)」を行い、余分な分げつが起こらないようにコントロールします。期間・量ともに水の管理をきめ細かく行うことで、栄養の行き渡った豊かな味わいの米になるのです。

こちらも分げつがよく進んでいて、「中干し」真っ只中の状態(写真左)。地面にヒビが入るくらい土を乾かすことで余分な分げつが制限されるそう。健やかな成長には、きめ細かな水の管理が欠かせません。
田んぼだけじゃない。
まわりの生き物とのつながりが、稲を育む。
7月初旬の田んぼの周囲には多くの生き物がたくさん見られました。つばめたちがチュピチュピと囀りながら忙しそうに田んぼの上を行ったり来たり。休む間もなく小さな虫を捕まえては雛が待つ巣に届けています。田んぼの中にはおたまじゃくしだけでなく、まだ尻尾が残っている状態の“新米カエル”の姿も!オタマジャクシを狙うゲンゴロウ、ヤゴ(トンボの幼虫)なども泥の中に潜んでいます。田植えの直後は、植えたばかりのやわらかな苗を狙って夜中に鹿が現れることもあったそう。

田んぼで見つけた小さな虫を、夫婦つばめが数分置きに雛たちに届けます。このつばめの巣があるのは、米農家さんの家の軒先でした。

7月上旬の田んぼでは、おたまじゃくしが続々とカエルへと成長。アマガエル、ヌマガエル、トノサマガエルなどカエルの種類もさまざま。
梅雨が明けて気温が上がってくると、米農家さんを悩ませるのが雑草問題。昔は米作りの手間の半分は雑草取りだと言われていたほどです。田んぼに生えた雑草は稲に必要な水や養分を吸い取ってしまうだけでなく、病害虫の原因にもなるため対策が不可欠!現在は必要最小限の除草剤を使って対策を行います。畦道に生える雑草は草刈り機で行います。除草剤を使わないのは、地中で畦を強化し水漏れなどを防いでくれている根っこを残すためだそうです。

すべての生き物とつながり、稲の成長を支えていく。「コ・ノ・ホ・シ」が守りたい、人と自然とのやさしい関係を、7月の田んぼで感じました。